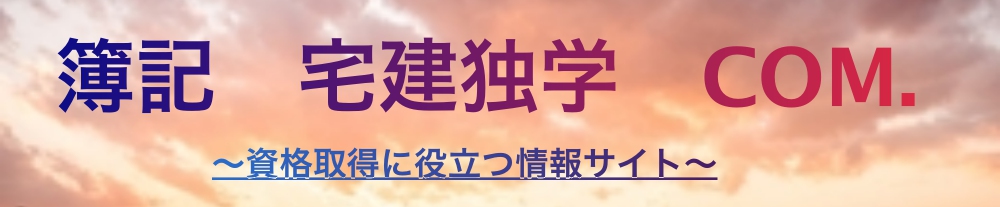今日は簿記とはなにかという事について、私なりにざっくり述べさせていただきたく思います。
簿記って何のためにするのか? と問われれば、勘定計算をするためだ、というのは当たり前です。
ではなぜ勘定計算をするのだ、と問われれば、現状を把握して将来どうするべきかを考える為、ということも当たり前だと思います。
いくら売り上げがあって、仕入れがかかって、人件費がかかって、家賃とかも・・・、結局いくらもうかったのか。
預金にはいくら残金が合って、在庫や売掛はいくらあるのか・・・。
これらの情報を得るには決算書や勘定元帳などを用いるのですが、簿記はこれらの書類を作る技法なのです。
つまり簿記は商売をする上で役に立つ情報を作るための技術、という事ができます。
ちゃんと商売しているとこれらの情報は重要ですよね。
それは大昔からも変わらなくて、簿記の発生は中世ヨーロッパのルネッサンス期だったようです。
ここでの簿記とは複式簿記を指します。
単式簿記としてはもっと昔からあったそうですが、複式簿記が確立されたのはこの時期だった模様です。
簿記には単式簿記と複式簿記があります。
私たちが勉強している簿記は複式簿記であり、一般的に簿記というと複式簿記という認識でよろしいかと思います。
単式簿記というのは、例えばお小遣い張などがイメージしやすいかと思います。
現金や預金など、使う基準となる科目を一つ決めるのです。
複式簿記とは違って、現金と預金の動きだけを見て、期首と期末の残高の差額で財産の残高を把握する手法です。
例えば、売上が預金に振り込まれたとあれば、単式簿記だと預金の帳簿に記録して終わりです。
複式簿記だと、
預金 / 売上 などと仕訳をきって、預金の帳簿と売上の帳簿の両方に記録します。
給料を預金から払ったとしたら、単式簿記の場合は預金の帳簿に記録して終わりです。
複式簿記だと預金の帳簿と給料の帳簿の両方に記録します。
単式簿記は楽でいいのですが、得られる情報としては限界がすぐに見えてしまいます。
例えば、この例で借金をしていた場合、期末の預金、現金の残高がわかっても、借金がいくらあるかわからないのです。
借金の帳簿には記録していないのですから。
だから、預金の残高が十分あるように見えて、儲かっているのかと安心していたが実はそのほとんどが借金によるものだった、なんてこともあり得るかもしれません。
複式簿記ならば、借金の帳簿にも記録しているので、借金の帳簿の残高を見ればわかります。
また、実際のもうけを調べるには、記録した帳簿から売上や軽費をピックアップして、集計しなくてはなりません。
対して、複式簿記はそれぞれの帳簿の合計を見ればすぐに残高が把握できます。
それを決算書にすれば、財産と債務がいくらあって、売上がいくらあって、軽費はいくらかかって、いくら儲かっているのか、すぐにわかります。
複式簿記は単式簿記と比べて、作業は二倍といってもいいのかもしれないですが、メリットは二倍どころではないと思います。
二つの側面から記録する事により、貸借の確認ができるので、情報の性格性も高まりますし、決算書から得られる情報量が違いすぎます。
かといって、単式簿記が悪いというわけではなく、取引がシンプルかつ少ない場合は作業が少ない分単式の方がいいケースだってあります。
ツールなので使いどころを選ぶ、ということですね。
一番最初にも述べましたが、簿記とは商売などを行うにあたって、お金に関する情報を作るための技術だと私は考えています。
法律的にもそうですが、日本の全ての会社でこの技術は用いられておりますし、言葉は違えど世界共通の技術です。
個人的には簿記って、もっともつぶしの効く技術なのではないかと、考えております。
簿記資格が人気あるのも当然だと思います、
宅建なども使える分野は広いですが、簿記は商売をする全ての会社や個人において使える技術ですから。